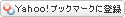平成24年5月28日、読売新聞(オピニオン)
ハーグ条約の批准と離婚後親子法
棚瀬 孝雄/中央大学法科大学院教授
専門分野 法社会学
1 はじめに
現在、ハーグ条約の批准が閣議決定され、その実施のための国内法整備が進められている。
条約の内容は、新聞等でも報道されており、ある程度の理解は共有されているが、しかし、政府から出されている条約施行のための国内法を見ると、日本の世論や家裁実務の現状を意識したと思われる変更が加えられており、これで、はたして、ハーグ条約の趣旨が活かされるのか、疑問もある。
ただ、条約の批准を梃子に、日本の離婚法を、国際的な水準にまで引き上げようという期待も強い。私個人も、学者として、ハーグ条約、及び離婚後親子法の比較法的な研究を進め、また、弁護士として、国際、国内双方の事件に関わってきた。その研究、及び実践から、日本の実務の現状を憂慮し、改革を主張している。
以下、まず、ハーグ条約の内容を、その理念と、基本的な仕組みが分かるような形で解説した後、国内法の改革にこの批准が持つ意味を検討したい。
2 ハーグ条約の枠組み
1)不法な連れ去り
この条約は、正式名称が「子の奪取に関する民事面の条約」とあり、国際的な子の連れ去りが起きた場合に、締約国が協力して、子を元の居住国に戻すための仕組みを合意したものである。また、それは、国際私法上の条約に分類され、とくに、連れ去りの圧倒的部分を占める、離婚前後の一方の親による、他方親の監護権を侵害する形の連れ去りに対し、背景となる監護権をめぐる争いの国際裁判管轄を定める国際条約でもある。
子を連れて帰国し、そのまま「事実上の監護親」として、別居を継続したまま、子を手元に置く場合もあるが、帰国した先の裁判所に、監護者指定、あるいは離婚を申し立てて、監護権を正式に認めてもらう場合もある。こうした子連れ帰国が、他方親の同意を得ずに、その監護権を侵害する形で行われる場合が、「不法な連れ去り」(「奪取」“abduction”)である。
2)返還原則
ハーグ条約では、前文に、「子の連れ去りから生ずる有害な結果」から国際的に児童を保護するために、締約国は本条約を結んだとある。連れ去りを防ぎ、連れ去りが生じた場合には、速やかに、その有害な結果を取り除くために、子を元の居所に返還しようとするのである。これが、この条約の骨格にある、英語の表現で、“summary return” と呼ばれる原則(「返還原則」)である。
この “summary” には、即座に、という迅速さと、そのために時間のかかる手続きは省いて即決の、という簡略さとの2つの意味が込められている。
前者の迅速さが必要なのは、一つには、もちろん、連れ去られて、他方親との関係が断たれた状態が続くことそれ自体が有害であり、速やかに他方親の監護権を回復する必要があることがあるが、もう一つ、監護に特有の問題として、子どもが大人に世話をされなければ生きられない、無力な存在であることから、連れ去りの状態を速やかに克服する必要があるからである。
実際、子どもは、無力なゆえに、連れ去られた環境に適応し、世話をしてくれる、連れ去った親に忠誠を示すようになる。そのため、子を連れ去って、他方親との関係を断ち切ることで、監護権を独占しようとする試みが後を絶たないのである。いわゆる、「連れ去り勝ち」である。それを許さないためにも、速やかに、また、子が示す忠誠(いわゆる「子の意思」)を考慮することなく子の返還を行うというのが、ハーグ条約の骨子である。
3)要件主義
この迅速な返還を実現するために、ハーグ条約では、外形的な事実として、監護権(婚姻中の共同親権を含む)をもつ他方親の同意を得ずに、一方の親が子を連れて国外に出ること、つまり、「不法な連れ去り」があったことだけ確認されれば、自動的に返還が命じられる、という形を取っている。
子の意思、つまり、子どもは元の居所には戻りたくない、私と一緒に住みたいと言っているといった抗弁が連れ去った親から出されても、それは、この返還の可否には一切考慮されない。同様に、婚姻中のあれやこれやの出来事が言われ、子どもにとって、私と住む方が幸せである、相手の親には子どもを適切に監護できない、といった抗弁も聞かれない。実質的な監護をめぐる議論に立ち入れば、必然的に審理が長引き、迅速な返還ができなくなるからである。
これが、“summary” のもう一つの、即決という意味である。法学的には、「要件主義」という。要件、すなわち、外形的な事実(連れ去り)に、直接、法的な効果(返還)が結びつけられ、審理も、この要件の確認のみを行うものとなるのである。
4)重大な危険
ただ、子どもへの虐待があって、返すことが明らかに危険である場合もなくはない。それは、条約でも返還を拒むことができる例外事由として規定されているが、しかし、この例外は、運用を誤れば、返還原則を危うくする危険もある。
実際、ハーグ条約制定の際に、その点が大論争になった。子への乱暴な扱い、心理的な虐待や、配偶者への暴力、暴言は、破綻する婚姻では、ほとんど常にと言ってよいぐらい、他方配偶者から非難として出され、離婚の有責性、さらに監護権や面会交流権の決定が争われている。
それゆえ、そこに足を掬われないようにしないと、審理は長引き、その間に、子どもも会えない親に頼らず、連れ去った監護親に依存するようになって、返還ばかりか、その後の親子の関わりすら断ち切られてしまう。その危険から、条約では、返還拒否の例外を、子に肉体的・心理的な危害をもたらす「重大な危険」がある場合と、言葉の上で明確に絞り込んでいる。
また、条約締約国の裁判例でも、例外を厳格に解釈することで、返還原則を守ることへの強いコンセンサスが見られる。
5)国際裁判管轄
このように、ハーグ条約の適用が争われる裁判では、不法な連れ去りがあれば、後は、重大な危険という狭い例外にあたらないことだけ確認して、即決で返還が命じられるのであるが、逆に、その審理から排除された、子の監護の実質的な判断は、子の、連れ去り前の本国(常居所)で行うというのが、条約の考え方である。これが、ハーグ条約の国際裁判管轄を定める、国際私法的側面である。
裁判権は、国家の主権作用であり、それぞれ主権国家が、自ら、どのように国籍を異にする者の間の紛争に裁判権を行使するか、あるいは拒否するか、その主権の行使として自由に定めうるというのが、国際裁判管轄の原則である。
しかし、そうであれば、子を連れ去って帰国した者が、その国の裁判所に監護権者の指定を求めて訴訟を起こしても、その国で、国際裁判管轄を認めて審理をすることもあり得ることになる。その場合、連れ去った者には、自分の国だから当然に地の利があり、連れ去られた者は、監護権を争うために、その国に行って裁判をする必要が出てくる。しかも、裁判は1回で終わらず、1ヶ月か2ヶ月おきに、半年から1年、時に2年もかかるとなると、経済的な負担だけでも大変である。最初から、争うのを諦めることもあるであろう。結果は、連れ去り勝ちである。
この困難があり、それが、結局、連れ去りを助長することになるとすれば、「連れ去りの有害な結果から国際的に児童を保護するために」は、国家間で条約を結んで、この連れ去った者が、自国の裁判所で監護権の申立を行うことを禁止する必要がある。それがハーグ条約であり、条約では、連れ去る前の子の原居住国が、排他的な国際裁判管轄を持つことに、各国が合意しているのである。
6)連れ去りの無効化
この排他的管轄を認めることで、条約の返還原則も生きてくる。連れ去りをしても、強制的に子どもを原居住国に戻し、そこで監護権を争わせることで、連れ去りの無効化、つまり、連れ去りをしても何の得もない仕組みが作り上げられるのである。ハーグ条約には、刑事罰はなく、連れ去り禁止を直接には規定していないが、実際に、この連れ去りの無効化を行うことで、連れ去りの禁止を実現しているのである。
連れ去るな、連れ去らず、まず、婚姻が行われているその国で、離婚後の子の監護の問題をしっかり取り決め、それから別れなさいというのが、ハーグ条約に結実した、世界の、離婚後の子の監護に関するコンセンサスなのである。
3 国内法への含意
1)連れ去り容認の国内法
ハーグ条約は、国際的な子の連れ去りを対象とするものであり、国内での連れ去りには直接関わらない。その意味で、今回、条約が批准されても、国内法が直ちに変わるわけではない。しかし、連れ去りの有害な結果は、国内での連れ去りであっても同じである。実際、日本の離婚の圧倒的多数が、今でも、一方の親が、無断で、子を連れて実家に身を寄せるなどして別居し、その後で離婚を求める、という形が取られている。
日本の裁判実務では、この離婚に至る過程での子連れ別居は、連れ去りとも呼ばず、黙認している。それは、判例の言葉でいえば、「監護を継続する意思で、子を連れて家を出る」ことであり、「子を置いて出られない」以上やむを得ない、というのである。また、そこには、監護を継続する、という表現にあるように、監護される子どもにとっても、親が別居しても継続して監護してくれることで、子の福祉が守られる、という判断もある。
しかし、この判例の考え方は、世界のコンセンサスから大きく隔たっている。
2)連れ去りの弊害
子どもは、自分を可愛がってくれていた親から、突如、理由もなく切り離されれば、大きなトラウマを経験する。それは、基本的信頼感の欠如として、終生残る傷にもなりかねない。
また、連れ去りは、連れ去られた親の怒りを当然に引き起こし、それがまた、怒りが怖い、連れ戻しを恐れるということで、いっそう、連絡を絶ち、居所を隠すことになる。もちろん、子との面会交流も拒否し、切り離しが行われていく。
その後、調停や審判が行われても、この連れ去りからくる切り離し、そして、怒り、恐れの負の連鎖が背景にある限り、親同士、対面して、離婚後の子の監護を冷静に話し合うことはできない。調停委員や、裁判官が間に入って、連れ去りの現状、つまり、「親権と離婚を認める」代わりに、面会交流を認める、という取引を成立させることが精一杯である。
しかし、連れ去って、子を手元に置いた者が、切り離した上、「会いたければ、離婚と親権を認めよ」として要求を押し通すことは、それ自体許せない、不法な行為であるが、それ以上に、そこにある非対称的な関係性が、結局、その後の親子の関係を歪める、という大きな問題を引き起こすことになる。
3)対等な共同養育
現在、世界があるべき離婚後の親子法と考えているのは、子が、両方の親と継続的、かつ直接の接触を維持することであり、また、両方の親が、それぞれ、離婚後も、子を家庭で育て、学校行事にも参加するなど、子との生活時間を可能なかぎりともに過ごすことである。
親は別れるけれども、子は、パパの家、ママの家と、2つの家を持ち、両方から愛情と養育を受けることで、強い親子の結び付きを維持するのである。もちろん、別れて暮らす以上、物理的な制約はあるけれども、可能なかぎり、この「共同養育」を実現することで、子どもは、離婚しても親を失うことはなくなるのである。
ハーグ条約が前提としているのも、両方の親が、親として子の養育を行うその監護権を、連れ去りの一方的な行為で破壊する、その問題性の認識である。国際裁判管轄を、締約国が、子の常居所地に定め、連れ去って自国の裁判管轄を求めても受け付けず、原居住国に返させて裁判を受けさせようとするのは、子どもと一緒に住んでいた国で、別れる前に、親が対等な立場で協議し、離婚後の取り決めをすることが、離婚後も対等な共同養育を実現する鍵である、という考えからである。
このハーグ条約の理念、そして枠組みは、日本の中の離婚でも当然に妥当すべきであり、ハーグ条約の批准が議論されている今、目を日本国内の問題にも向けて、あるべき離婚後の親子法を構築すべきである。
実際、連れ去りを容認しているのは、先進国の中では日本だけである。早くこの現状を克服し、離婚で子どもが親を失わないで済むような社会になることを願っている。