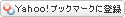令和3年3月27日、Yahoo!ニュース
親権をもてなかった母親への冷たい視線――子どもと別居する苦しさと葛藤
毎年、20万から25万件で推移する離婚件数。子どもの親権はたいてい母親がもつが、父親のケースもある。この場合、親権をもたなかった母親に対してさまざまな憶測が飛び交う。「子どもがなつかなかったのでは」「何か悪いことをしたのでは」……。親権をもたない父親に比べて手厳しい。なぜ「別居母親」は批判的な目で見られがちなのか。2人の当事者から話を聞き、実態を探った。(取材・文:上條まゆみ/Yahoo!ニュース オリジナル 特集編集部)
「別居母親」は少数派
中部地方に住む西川千佳さん(仮名、47)は、16歳と13歳の娘の母親だ。11年前に離婚し、子どもたちとは別居している。
「本当は子どもの親権をもち、一緒に暮らしたかったのですが、無知と不運が重なって、親権を元夫にとられてしまいました」
厚生労働省の調査によると、令和元年の離婚件数は20万8496組。そのうち未成年の子どもがいるのは11万8664組で、20万5972人の子どもが親の離婚に巻き込まれている。
日本の法律では、離婚後の子どもの親権は父親か母親のどちらかがもつことになるが、調停で母親が親権をとる割合は90%以上。離婚後、ほとんどの子どもが母親に引き取られている。
千佳さんは30歳のとき、社会人サークルで出会った一つ年上の男性と結婚した。おだやかで友だちを大事にしていて、信頼できる人だと感じた。
元夫は、父や妹とともに家族で工場を経営していた。母親は離婚して、家を出ていた。
自営業の家に嫁ぐことに千佳さんはある程度の覚悟をしていたが、実際は想像以上に息苦しかった。
「財布は義父が握っており、私は食費を渡されるだけ。それも月何万とかじゃなく、はい1万、はい3万みたいにその都度もらっていました。『なくなったら言えよ』と言われていましたけど、やっぱり言いにくいんですよね。買い物に行く店も決められていたし、主婦として家庭を切り盛りする自由はまったくありませんでした」
子どもが生まれてからも、義父の支配は続いた。
「今日は散歩に行けとか、いまから公園に行けとかタイムスケジュールまで決めてくる。その一方で、工場の事務の仕事も変わらずこなせ、と。私が子どもを保育園に預けたいと言ったら、『母親失格だ』と責められました」
たまの休みに、どこに遊びに行くかも義父の指示。家族4人、水入らずで出かけたことはほとんどない。「実家と縁を切れ」とも言われた。次女の出産のあと、正月に実家に帰ることも許してくれなかった。
娘を連れて家を出る
義父と離れて家族4人で暮らしたい。元夫に訴えたが、「考えてみるね」と言うだけだった。千佳さんはたまりかねて、実家に子どもを連れて帰った。
「長女の(幼稚園が)春休み中のことでした。家出という強硬手段に出れば、元夫も真剣に向き合ってくれると思ったんです」
しかし、元夫からは何の連絡もない。千佳さんは、新学期の始まりに合わせ、とりあえず子どもだけ家に帰した。次女の入園式には夫婦そろって参列したが、翌日から元夫と連絡がとれなくなった。
メールをしても電話をかけても無反応。焦った千佳さんは、慌てて家に戻った。家の中に入ろうとすると、義父と義妹に「もう帰ってくるな!」と追い返された。元夫は見て見ぬふりをしていた。
千佳さんはしばらく実家で呆然と過ごした。子どもに会えない状況を変えるため、弁護士に相談した。そして、家庭裁判所に夫婦円満調停(夫婦関係調整調停)と、子どもの引き渡しおよび監護者の指定を申し立てた。監護者とは、子どもを引き取り、生活をともにし、身のまわりの世話をする人のことだ。
それらの手続きと並行して仕事を探し、総合病院の事務職として働き始めた。子どもを引き取るつもりだったので、時間に融通のきく職場を選んだ。しかし、千佳さんの思いとは裏腹に、娘2人を引き取ることはできなかった。
知らなかった調停のルール
家庭裁判所が親権者や監護権者を決めるときの基準の一つに「母性優先の原則」がある。その一方で、「監護の継続性の原則」も重視される。これは、これまでに子どもが育ってきた環境を継続したほうがいいという考え方だ。
そのほか、経済状況を含めた監護態勢や、兄弟・姉妹は一緒に育てたほうが子どもにとっては利益があるという事情(兄弟姉妹不分離の原則)も勘案される。
千佳さんが子どもを引き取れなかったのは、「監護の継続性の原則」などが適用されたからだ。2人の娘は祖父、叔母、父親と安定して暮らしている。どちらか1人を千佳さんが引き取るのも望ましくない。
千佳さんは自分が調停を起こすまで、そのような原則があることを知らなかった。
「子どもを誰がどこで育てるのかを、いちから決めるのが調停だと思っていました。子どもをいったん家に帰してしまった時点で、すでに負けレースだったなんて……」
子どもと暮らすつもりで選んだ職場はシングルマザーが多く、話題は子どものことばかりだった。
「シングル家庭が大変だということはよくわかるのですが、私には、愚痴が全部、自慢話に聞こえてしまうんです。私だって子育ての苦労を味わいたかった……」
同僚は親切で、千佳さんの事情についてはふれてこなかった。しかし、同僚の心の中に「なぜ子どもを引き取れなかったの?」という思いがあるのが透けて見えた。
「もちろん、私に直接、そういうことを言ってくる人はいません。でも、たとえば、有名人の離婚問題が話題になったときなどに、(親権をもたない母親に対して)『母親なのに』といった世間の本音がわかるんです」
自信が生まれ前向きに
千佳さんは調停の結果、子どもと月1回の面会交流が認められた。その後、離婚が成立。元夫が親権者となり、千佳さんは月4万円の養育費を払うことになった。子どものために、それに5000円上乗せして払っている。
「調停もあって子どもとは8カ月も会えませんでした。その後も、相手方の都合で面会交流は年1回程度、しかも相手家族の監視付き。母子だけで月1回コンスタントに会えるようになったのは、別居から4年経ってからです。面会交流で久しぶりに会えるというとき、私としては話が盛り上がらないんじゃないか、拒否されるんじゃないかって不安でいっぱいだったんです。でも、子どもたちは昨日まで一緒にいたかのような勢いで、『やあ!』ってふつうに接してくれたんです」
その後の面会交流もごく自然に、ごはんを食べて、買い物をして、学校の話を聞いたりした。そうした交流を繰り返していくうちに、千佳さんの中に「ああ、もうこの子たちから私の存在が消えることはないんだ」という自信のようなものが湧いてきた。お乳を飲ませ、添い寝をし、抱きしめてきた母親の肌の記憶は、子どもたちから消えることはないと考えるようになった。
離れて暮らしてはいるけれど、子どもたちの中にしっかりと母親が息づいている。そう気づいてから千佳さんは、人生を前向きに考えられるようになった。
「子どもが誇らしいと思える母親になりたい。困ったとき頼れる母親でいたい」
日々、その気持ちを胸において生きる千佳さんは、まぎれもなく「子育て」をしている。
「母親なのに」世間の視線に傷つく
「親権を欲した母親が、親権をもてないのはつらいでしょう。でも乳幼児は母親が衣食住の世話をするべきという『3歳児神話』は、真実ではありません。愛情をもって接してくれる大人がいれば、父親でも母親でも保育者でも、きちんと子どもは育ちます」
そう話すのは、母性研究の第一人者として知られる大日向雅美さん(恵泉女学園大学学長)。長年、女性のライフスタイルや子育てについて研究し、母親の役割の重要性を過度に強調する傾向に警鐘を鳴らしてきた。
さまざまな事情で子どもを手元で育てられない母親も、ある意味、「母性愛神話」の被害者だ。「母親なのに」「母親のくせに」という世間の視線に深く傷つく母親も多い。
矢代早希さん(仮名、41)もまた、娘(12)と別居していることに苦しんできた母親だ。
元夫は、早希さんに暴力を振るったが、娘には優しかった。娘は当時3歳。離婚しても一緒に子育てをしていこうと話し合い、最終的に元夫が親権をもち、早希さんが監護権をもつことにした。親権者と監護権者は一致することが多いが、別々になることもある。
早希さんはアパートを借り、娘と2人で暮らし始めた。定期的に面会交流を行い、週末には娘が元夫の家に泊まることもあった。
4カ月後、元夫が復縁を求めてきた。早希さんが断ると、元夫は娘を帰してくれなくなった。
「(自分のところに)戻ってこないなら、もう娘を会わせないよ、って。実際、それから3カ月間、私は娘と会えませんでした」
耐えられなくなった早希さんは、家庭裁判所に面会交流と親権者変更の調停を申し立てた。しかし、その時点ですでに元夫と娘が数カ月間、問題なく暮らしていることから「監護の継続性の原則」が重視され、親権者変更は認められなかった。
「面会交流は認められましたが、わずか月2回でした。まわりの人たちに『これでも相場より多いんだよ』と慰められましたが、私には全然、足りなかった。それまで毎日一緒にいたのに。まさに片腕をもぎ取られるような痛みを味わいました」
家族連れを見るのがつらくて、ショッピングモールに行けなくなった。スーパーで幼い子どもの「ママ!」という声を聞くと思わず振り返った。
「まさか元夫がこういう形で親権を振りかざしてくるとは思いませんでした。でも、それを見抜けなかったこと、復縁を断ったことは、私のせい。すべて私が悪いんだと思ってしまい、自分のすべてに自信がなくなりました」
狭い田舎町はうわさがすぐに広まる。なぜ子どもと離れて住んでいるのか、弁解の機会もないまま、早希さんは「訳ありな母親」と見られた。仕事相手の男性と喫茶店で打ち合わせをしている姿を目撃され、不貞を疑われたりもした。
保育所のママ友のほとんどは、早希さんから離れていった。詳しい事情がわからず、どう接していいのかわからなかったのかもしれない。
「いちばん傷ついたのは、『私だったら耐えられない』『私だったら死んでしまう』という言葉でした。耐えられなくても耐えるしかないし、そう簡単に人間って死ねないですよ」
「幸せなお母さん」になるしかない
早希さんは町から引っ越すことも考えた。しかし、娘のそばを離れるわけにはいかず、堂々と生きていくことを選択した。
「『相手が悪い』『社会が悪い』と泣いて、かわいそうなお母さんでいればいるほど、世間から『本当に?』『実はあなたも悪いんじゃないの?』とツッコミが入る。何をしていても、どうせ言われてしまうなら、誰から見ても幸せなお母さんになるしかないと思ったんです」
離れて暮らしていても子どもといい関係が築けるよう、子育てやコミュニケーション術を学んだ。やりがいのある仕事につけるよう、自己研鑽にも励んだ。
別居母親同士が集まる自助会にも参加し、面会交流支援にもかかわった。いまは母親の自立と親子のコミュニケーションを手助けする活動をしている。
「別居母親という超絶マイノリティーだけど、子どもも仕事も自分の時間も全部ある。こんな幸せな生き方はないって実感しています」
早希さんは3年ほど前、元夫と週交代での共同養育が実現した。パパともママとも仲良くしたいという娘の希望が叶えられた形だ。早希さんもこのスタイルに納得している。
多様化する子育て
家族のかたちは一つではない。母親のありようはさまざまだ。かつて、子どもを保育所に預けて仕事をする母親を「育児放棄」と蔑む時代もあった。前出の大日向学長はこう語る。
「彼女たちが語ってくれた物語には胸が痛みましたが、こうして声を上げてくださったことで社会に一石を投じることができたのではないかと思うんです。『育児がつらい』という母親の声から子育て支援が生まれたように、当事者が声をあげ、その苦しみが明るみに出ることから、社会は確実に変わっていくでしょう」
多様な子育てのあり方を認め合うことが、別居母親を差別から救う。偏見の目で見られがちな子どもも救う。不意にどんなことが起こっても、誰もが生きやすい社会が求められている。
- 上條まゆみ(かみじょう・まゆみ)
1966年、東京都生まれ。教育・保育・女性のライフスタイルなど、幅広いテーマでインタビューやルポを手がける。近年は、離婚や再婚、ステップファミリーなど「家族」の問題を追求している。
アクセス数
総計:631 今日:1 昨日:0