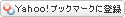平成29年10月22日、土井法律事務所(宮城県)ブログ
ある国立大学教授の大森貴弘氏批判への疑問 必要なことは、親子断絶の危険性についての理解あるいは、子を思う親の気持ちへの理解ではないかと思う理由
ある国立大の法学部教授が、朝日デジタル「私の視点」に大森貴弘氏を名指しして批判した記事が掲載されました。彼女は以下のように大森氏を批判しています。
http://digital.asahi.com/articles/DA3S13186771.html
「兵庫県伊丹市で面会交流時に起きた痛ましい子殺し事件について「原因は親子断絶による父親の精神状態の悪化にある。面会交流が継続されていれば事件は起きなかったはずで、親子断絶の問題を告発 した事件と言える」とする見解が、何でもありのネット空間ではなく、新聞に掲載されたことに、深い悲しみを覚える。
これは、大森氏の文章に対して、ネット空間のような何でもありの主張であり、新聞に掲載されることは言語道断だという、極めて辛辣な批判です。彼女のこの主張は、仲間同士の閉ざされた人間関係の中での発言ではなく、これまた新聞という不特定多数人に向けた主張のはずです。そうだとすると、なぜ、何でもありのむちゃくちゃな主張であるのか、その理由を説明しなければ、失礼であり、品位を欠くものだと、私は思います。
その後の彼女の論は、日本の法律は家庭に入りにくい設計になっているが、設計された明治時代は家という大人数で子どもを育てていた。両親に問題があっても、他のまともな大人が子どもを守っていたという趣旨のお話をされ、現在は、その安全弁が失われ、児童虐待に対する予算も体制も日本は貧弱だと展開されています。面会交流も大事だが、加害者の加害を見抜く制度設計が必要だとして、これがない親子断絶防止法を批判します。
そして「私は伊丹市の悲劇の詳細を知らないが、仮に父親が3カ月間、子に会えなくて精神的に病んだとしても、悲劇の責任は、面会交流を試行錯誤した母親にあるのでは決してない。子を守れなかった責任は、親を放置して育児を支援しなかった、私たち日本社会の無責任な無策にある。」と結んでいるのです。
第1に、大森氏の論考が、伊丹の事件で、子どもが死んだのが母親の責任だなどとは言っていないのですが、彼女の話の流れは、さも大森氏がそのような主張をしているように読み手に誤解を与えることになります。 私の弁護士としての体験からですが、子どもを連れて別居した母親は子どもに取って父親の愛情を受けることに、あくまでも反対だという人は少ないという実感があります。母親に対して適切な働きかけをして、周到に準備をして母親の不安を軽減した上での面会交流は例外的なケースを除いて実行されます。むしろ、母親に対して子どもを父親に合わせるなという無責任な「支援者」がいるために、面会を拒否するケースが大半です。この「支援者」として、行政や警察、弁護士や医者、学校等様々な職種の人たちが子どもが自分の親に会うことを妨害しているということが実情です。大体は、すでに論拠がないと否定されつくされているレノア・ウォーカーのお説をさらに劣化させて繰り返し母親に吹き込んでいるのです。新しいケースでデジャブ―のように聞かされるたびにうんざりしてしまいます。母親がそれを信じる原因として、夫の家族に対する日常の行動に問題がある場合もありますが、それよりも、母親の体調の問題からの精神的な不安定が要因となることが多いようです。体調の問題とは、漠然とした不安感、疎外感、孤立感です。実際の離婚事件で母親が診断された疾患として、甲状腺機能異常、産後うつ、月経前緊張症、全般性不安障害、うつ病、パニック障害などがあります。このような不安状態の中で、行政や弁護士、警察や医師、学校関係者から、会わせてはいけないとアドバイスされると、合わせること自体が不安になるということもあるでしょう。
母親たちは、逃げることで、不安のほかに恐怖まで植え付けれられているのが実情です。現在の逃げるという政策は、即ち子どもを連れて逃げるということですから、当然に父親から子どもを引き離す政策だということを意味しています。この政策を転換するべきだということが、本来提言されるべきことだと思います。それが親子断絶防止法かといわれれば、極めて不十分であることは私も異論がありません。親子断絶防止法は、当初の案から大幅に後退してしまっており、メリットが少なくデメリットが増えてしまったと感じています。一番の問題は結論を提示しているだけで、その結論にどのように誘導するかという肝心の政策がない点です。
第2に、彼女の論の疑問点として、親子断絶によって精神状態の悪化が起きたことを論難しているように読めることです。
現実に、父親や母親がわが子と会えなくなることで、様々な精神症状が現れます。これまで精神科医がうつ病などの抑うつ状態、転換性障害、不眠症などと診断した人たちを実際に見ています。突如電話をしたくなり、相手の事情もかまわずに自分の不安を語りだす人、ほとんど日常的に涙目になっている人、誰彼構わずに攻撃的になる人、多かれ少なかれ、異常行動が見られます。
日本人は、少なくとも江戸時代までは、子煩悩で有名でした。山上憶良の歌から始まり、モースの「日本その日その日」等、子どもがいかに大切にされていたかを物語る資料は尽きません。自分の一部だと思っている子どもと引き離されることで、精神的な不具合が生じることは当然なことでしょう。
現在の母子を逃がし、父から断絶するという政策が人の精神を病ませる実例は枚挙にいとまがありません。
家庭内暴力があり、命の危険がある場合はやむを得ないでしょう。しかし、現実に家族が分断されるケースは、私が知る限りそのような危険のないケースがほとんどです。むしろ、心身を蝕むケースの本当のDV事案では、なかなか法制度によって救済されない問題点があると感じています。支援制度を悪用して不貞相手の男性と同居していたケースも少なくありません。DVがないにもかかわらず、DVがあるように思いこんでしまっているケースも多くあります。この点の原因としては、国立大学の教授の見解が支持されるべきであり、夫婦、家族が孤立していることに問題があると私も思います。但し、孤立しているため、加害者が被害者に加害をするという単純な話ではなく、お互いが、自分を客観的に見ることができず、疑心暗鬼をだれも止めてくれないということ、ちょっとの工夫をアドバイスされれば、みんなが幸せになるのにということなのです。この違いは決定的だと思います。
逃がす政策が人を狂わせ、凶暴化させ、あるいは破れかぶれにさせ、あるいは思考力を奪い、さらなる悲劇を生んでいるということは真実だと思います。そのような側面が確かにあり、少なくないケースで見られるにもかかわらず、なかったことにされることはどうしても納得できません。まさに数の暴力です。私は、人権侵害が行われていると思います。女性の権利を守る名目で、子どもと会えない親の人格が国家によって否定され、子どもが両親から愛情を注がれる権利が理由なく奪われ、子どもの親を絶対的な悪だと子どもに対して繰り返し吹き込む、そのような野蛮なことが横行していると声を大にして言いたいのです。
第3に、彼女の主張で、もし、親子の引き離しによって父親の精神破綻が生じて暴力に出たということ自体を否定していたとしたら、それは元々父親は子どもを殺すような粗暴な人間だったということを主張しているのでしょうか。そのように読むと論述自体が一貫しているように読めるのです。彼女は、大森氏のどこがどのように何でもありなのか説明をしていないので、不明ではあります。しかし、もしそうだとしたら、人間観に問題があるように感じてなりません。
私は、長年刑事弁護を担当しているわけですが、生まれながらに犯罪を実行する人などいないと感じています。みんな理由があって逸脱行動にでるということです。弁護人の仕事は、罪を犯した人とその理由を考え、理由を除去し再犯を予防することだと整理できると思います。伊丹の事件の理由の一つとして、子どもと過ごすことのできない絶望感や、そのことによって発症した精神疾患ということは、可能性があることを否定する事情はないでしょう。なんでもありというような荒唐無稽の話でないことだけは確かです。
気になるのは、彼女の論拠の背景として、妻が子どもを連れて別居するというそれだけのことから、別居の理由が夫にDVがあったからだという決めつけがないかということです。実際にそのような別居事案において暴力と呼べる自体がないことが多くあります。精神的虐待といっても、日常よくあるいさかいをもって虐待と呼んでいるケースがほとんどだと実感しています。いずれにしても、そのようないわゆるDV冤罪の事案は少なくありません。このようなDV冤罪を作り出し、父親の精神を破綻させ、子どもから父親と会う権利を奪い、子どもから父親を肯定する権利を奪う最大の原因が、このような類型的な決めつけ、ものの見方です。一言で言って差別です。
松戸家裁の事例では、父親のDVは裁判所でついに認定されませんでした。当事者がDVを裁判家庭において主張することはともかく、ひとり親支援NPOの代表や、武蔵大学社会学教授は、何も事情を知らないくせに父親をDV夫だと決めつけて、SNS等で流布したことで、刑事告訴をし受理されたとのことです。伊丹の事案は、父親も自死してしまいましたので、告訴をする人がいないのかもしれません。しかし、法律家は、事情知らない事案では、当事者を非難するコメントをしないということが最低限の矜持だと理解しています。何らかの決めつけがあったならば、法律家としてのコメントとは言えません。このルールは実務家だけで研究者は例外なのでしょうか。
現在の親子断絶防止法を批判することは自由でしょう。しかし、そのことのために、多くの人たちが傷つくことを謙虚に考えるべきだと思いますし、実際に起きている現実をぜひ知って、みんなが幸せになる方法を考えていただきたいと考えてやみません。みんながということが無理ならば、せめて子どもが自分の親を否定することを押し付けられた場合の、子どもの将来に起きることを考えていただきたいと思います。
以下引用。
「離婚後の子育て 共同親権で親子の関係守れ」と題した大森貴弘氏の「私の視点」(9月21日付)を読んでショックを受けた。兵庫県伊丹市で面会交流時に起きた痛ましい子殺し事件について「原因は親子断絶による父親の精神状態の悪化にある。面会交流が継続されていれば事件は起きなかったはずで、親子断絶の問題を告発 した事件と言える」とする見解が、何でもありのネット空間ではなく、新聞に掲載されたことに、深い悲しみを覚える。
先進国の家族法と日本家族法との違いは、離婚後の共同親権の有無だけではない。両親間のトラブルに対する制度設計がまったく異なっている。明治政府は30年をかけて西欧法に倣った近代法を立法した。しかし明治民法の家族法部分については、「家」の自治にすべてを委ねる、独自の極端な法を立法した。離婚を必ず裁判離婚とするような西欧法は、手間のかかる不要な国家介入だと判断したのである。当時は、まだ自営業を担う「家」が中心の社会で、人々は地域共同体や大家族に包摂されて生活しており、親に問題があっても子どもたちはまともな大人と触れあうことで健康に成長できた。この社会的安全弁は、失われた。
戦後の民法改正は「家」の自治を当事者の自治に変えただけだ。西欧の裁判所であれば、家庭内暴力(DV)被害者が助けを求めれば、加害者に別居命令を出し、養育費を取り立て、従わなければ刑事罰を加える。しかし、日本のDV被害者に残されているのは、逃げる自由だけである。DVは深刻な児童虐待であり、脳の成長を損傷する度合いは、肉体的虐待や育児放棄よりもむしろ大きいといわれる。そして児童虐待対応にかけられている公費も、日本は西欧諸国よりはるかに少ない。
もちろん離婚後も親子の交流があるほうが望ましく、子の奪い合いにはときに強制力のある介入も必要である。しかし、それは物理的・精神的暴力から子を守りながら行わなければならない。パーソナリティーの偏りや精神的暴力の有無などを見抜く力のある精神科医や臨床心理士などのプロが調査・介入して、加害者に働きかけてリスクを軽減して初めて可能になる。親子断絶防止法案は、これらの支援の保障なく、当事者への義務づけを定めるもので、弊害が大きい。
私は伊丹市の悲劇の詳細を知らないが、仮に父親が3カ月間、子に会えなくて精神的に病んだとしても、悲劇の責任は、面会交流を試行錯誤した母親にあるのでは決してない。子を守れなかった責任は、親を放置して育児を支援しなかった、私たち日本社会の無責任な無策にある。
アクセス数
総計:2162 今日:4 昨日:1