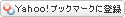令和5年1月25日、Bloomberg
親の離婚で子どもが板挟みに-共同親権導入に賛否の声
北條康雄さんはある日、6歳になる息子が玄関で「妻の方をきょろきょろと見て、どうしたら良いか分からない表情」を浮かべているのを目にした。
数日後、仕事から帰ると2人ともいなくなっており、家には妻の弁護士から離婚調停の申し立てを伝える通知が残されていた。
それから約1年、埼玉県にある2階建ての自宅に一人で暮らす北條さん(49)は、自分の子に会えないつらさをかみしめている。「同じ年齢ぐらいの子ども連れの人を見掛けると、なぜ自分はこんな当たり前のことができないのだろうと息苦しくなる。特に休日の公園などは一人ではとても近寄れない」と話す。
北條さんは監護者指定および面会交流などを求めているが、日本の法制度の下ではそれらの実現は容易ではない。ブルームバーグが取材した北條さんら男女十数人の親たちは、離婚後に子どもと会えなくなっただけでなく、100年余りの歴史の中で、政権の優先課題に応じて変遷し構築された曖昧な家族法制に阻まれている。
日本の子連れ別居
日本の親権は、「親権(医療・進学・居住などをめぐる重要事項決定権)」と「監護権(身の回りの世話)」の2つに大きく分かれる。離婚すると、父母どちらかに全親権に相当する権利が与えられることが多く、もう片方の親は子どもの人生からほとんど締め出されるリスクがある。離婚の手続きが簡単な上に、裁判所の介入が小さい日本において、排他的な単独親権の制度は婚姻関係の破綻をずっと複雑なものにしている。
日本は主要7カ国(G7)で唯一、離婚した夫婦に法律上の共同親権を認めていない。離婚の大半は協議か調停で解決されるが、合意できなければ裁判を行う。8割以上のケースで母親が親権者となっており、調停や裁判離婚に限れば、この割合は9割に上る。裁判所が命じる面会交流は1カ月につき数時間に限られることもある。
一方の親が他方の親の同意なしに子どもを連れて出ていくことは珍しくない。家庭内暴力(DV=ドメスティックバイオレンス)が疑われる事案などもあることから、正当な行為だと見なされることが多い。日本の裁判所や法律は、主に育児を担っている親が子どもと別居する行為を容認している。一方、残された親が子どもを連れ戻そうとすれば、違法な連れ去りと判断されることが多い。
しかし、こうした状況が近く変わるかもしれない。家族法制を他の国々の制度により近いものにする画期的な提案が昨年11月に法務省から示された。離婚後の共同親権を導入する案も盛り込まれている。
同案の賛成派はこうした改革が大きな社会的・経済的利益につながると主張。反対派は特に虐待が疑われるような離婚のケースで、事態を悪化させる可能性があると警告する。双方とも政府の介入がもっと必要だという点では一致している。
母親が親権を獲得するケースが増加
日本では20世紀前半ごろまで、ほぼ全てのケースで父親に親権が与えられ、離縁された妻は実家に戻るよう迫られた。父系中心の19世紀の「家制度」に由来している。
しかし第2次世界大戦後、単独親権の制度が導入され、裁判所が子どもの親権を主たる監護者に与える傾向が定着していった。日本経済は1946年から76年の間で55倍に飛躍した。しかしこの経済成長の背後で、長時間労働の「サラリーマン」の台頭に伴う配偶者控除といった制度は、女性を家にとどめるか、働く場合でもパートタイム労働にとどめるよう促すインセンティブとして働いた。働く女性は減り、母親に親権が与えられるケースは急増。その一方で養育費の未払いに対応する制度が不十分なこともあり、夫と別れて子どもを引き取った女性の生活は苦しくなった。
この数年、単独親権制度を巡る批判がますます高まっており、離婚後も子どもと関わりたいと訴える親たちによる集団訴訟が相次いでいる。北九州市立大学の濱野健教授(文学部)は「日本人は従来、離婚して子どもに会えないのは仕方がないことだと諦めていた。今では多くの人が諦めることができなくなっている」と述べた。
支払われない養育費
2021年1月、上川陽子法相(当時)は、養育費が支払われない問題や親子交流の断絶といった子の養育への深刻な影響に懸念を表明。昨年11月、国の法制審議会の部会は「家族法制の見直しに関する中間試案」を取りまとめた。その中で、共同親権の選択肢のほか、一定の養育費を支払う義務が生じる新しい制度や、養育費の請求にかかる負担を軽減するための試案も示されている。
ただ、多くの専門家は共同親権の導入が親権争いの特効薬になるとは予想していない。紛争の根底には、家庭に潜むあらゆる暴力から個人を保護するシステムの貧弱さや、日本社会にはびこるジェンダー不平等がある。
未成年者の人口が減少している日本で、両親が離婚した子どもの数は年間約20万人と、50年前の2倍に増加。21年の政府調査によれば、そうした子どもの3分の1は別居親との関わりが最終的に絶たれているという。
1993年から断続的に日本に居住し、日本における離婚に関する著作がある人類学者のアリソン・アレクシー氏は「日本では、片親を失うことで子どもの心がどれほど傷付けられるかについて十分な認識がない」と述べた。過去40年間の調査60件に関する2018年の分析は、共同親権の対象となった子どもは心理的・身体的健康により良い影響が認められると結論付けている。
早稲田大学・法学学術院の法学部教授で、法制審の部会委員を務める棚村政行氏は、「家族に対する国家介入はしない方がよい、家族自身がやればよい」との考え方から「日本の家族法では家族が責任を負ってきた」と説明。「離婚後も共同で養育する選択肢が一切ない現状の制度は、社会の実情にそぐわない」ため、共同親権の選択肢も含め「さまざまな家族や親子の在り方に合った法的な仕組みが必要」だと述べた。
棚村氏はさらに、法改正にとどまっては「絵に描いた餅」だとし、養育費の確保を促すなどひとり親家庭の支援を強化する必要があるとも指摘した。
この40年間で日本の母子家庭は46%増えた。うち養育費を常に受け取っている家庭はわずか28%で、養育費の総額は月平均5万485円。養育費は母子家庭の家計全体の16.2%を占める。こうしたこともあって、日本は経済協力開発機構(OECD)加盟国の中でひとり親世帯の相対的貧困率が最も高い。
日本の母子家庭の子ども2人に1人が相対的貧困層にある。
昭和女子大学の宮坂順子研究員は、夫との離婚交渉や育児を一手に担う「プレシングルマザー」は、「最も過酷な状況に置かれたシングルマザーだ」と指摘。実質シングルマザーであるにもにもかかわらず、法的に婚姻関係が継続しているため、制度的に「ひとり親世帯」とは見なされず、公的支援はほとんど受けられないという。
制度の狭間に置かれるプレシングルマザーの多くは、「経済的にも精神的にも疲弊してしまい、離婚後の生活準備を行う余力もないのが現状だ」と宮坂研究員は見ている。
ブルームバーグ・エコノミクスのシニアエコノミスト、増島雄樹氏は「新しい共同親権の制度は、より多くの子どもが高等教育を受け、貧困の再生産を生まない持続可能な仕組みとなる可能性を秘めている」と分析
「追加的な財政負担も限定的で、人的資本の蓄積を通じて日本経済の長期的な成長に寄与することが期待される。共同親権によって離婚時に養育費を夫と妻で負担を協議できる制度を作ることは、ひとり親の子どもが受ける教育水準を向上させ、現在OECDで加盟国平均より大幅に高い日本の相対的貧困率を改善させる要因となる」と指摘した。
増島氏はさらに、「高齢化が進み、医療・年金の支出が年々増える中で追加的な財政支出には限界もある」とし、「養育費を両親で負担する新しい公的枠組みを通じて、支払いの『逃げ得』や親権の『囲い込み』を防ぐことは、マクロ的観点からも日本経済にプラスになるのではないか」と述べた。
親権争い
子どもの親権や面会交流を巡る争いはますます激化している。最高裁判所によれば、2020年には子どもに関する調停・審判の数が07年の2倍余りに増えた。調停の平均期間は約10カ月と、過去最長となった。
子どもを巡る夫婦の争いが激化
係争の増加は、家庭および職場における変化とも関連しているようだ。週60時間以上働く男性労働者の割合は2020年に8%と、1990年の22.4%から減少。育児休暇制度の拡充もあり、育休を取得する父親の割合は過去5年間で3倍に拡大し14%となった。ただ、妻が家事や子どもの世話に費やす時間はなお夫の4.5倍だ。
それでも日本の男性は子育てでより大きな役割を果たしつつあり、それに伴って離婚の際に親権を争う人も増えている。
北條さんはそうした男性の一人だ。1996年に大学を卒業し、道路や河川などのインフラ整備の仕事に携わっている。2012年に結婚し数年後に息子が生まれた。
北條さん夫妻は昨年夏、結婚から9年を経て調停手続きに入った。家裁調停委員の昨年9月の調査報告書は、息子の「父に対する拒否や不信感」に言及。北條さんから提供された同報告書のコピーによれば、「幼少の子にとっては、その出生時からの継続性が重要であること」と「長男自身も母と一緒に生活することを強く望んでいる」ことから、「母による現状の監護態勢を大きく変更するべき事情まではうかがえない」としている。その一方で、こうした状況に置かれた子どもは「別居親に対して同居親と同じ立場に立った否定的な言動を取る」傾向があるとも指摘している。
北條さんの妻はコメントを控えている。北條さんは息子と会えないまま、調停は不成立となった。手続きは審判へ進んだが、決着するころには息子に完全に疎外されてしまうのではないかと心配している。
神奈川法律事務所の大村珠代弁護士は「面会交流を申し立てても半年や一年以上かかることもある。その間に良好な親子関係が崩れてしまう危険性が高い。別居したらすぐに会える仕組み作りが不可欠だ」と話す。
作花法律事務所の作花知志弁護士によると、「片方の親が勝手に子どもを連れ去ってしまい、会わせないと主張した場合、現状の法制度では、子どもを取り戻すことは非常に難しい」という。最高裁のデータによれば、この10年間に約1000件の「子の引き渡しの強制執行」が認められたが、引き渡しに成功した割合は約3割にとどまる。
日本ではそうした命令を他国と同じようには強制できないと、同志社大学のコリン・ジョーンズ教授は指摘する。家庭裁判所の判断は「最終的にあまり意味がない」という。
斎藤健法相は親権制度について、現時点で大臣として意見を言うべきではないとし、「多くの人の意見に耳を傾けながら、結論を出していきたい」と述べた。
最高裁の広報によると、子の監護に関する事件については、個別の事情を考慮しつつ、「子の利益を最優先にした運用がされている」という。子の引き渡しの強制執行については「子の心身に重大な影響を及ぼさないように配慮」しながら行わなければならないと指摘。執行できない主な原因は引き渡されることへの子の拒絶や親、祖父母の抵抗だとした。
日本で共同親権に反対する声が一部で上がる理由の一つは、離婚の原因にDVの懸念があることが多いことだ。
警察庁によると、配偶者などパートナーからのDV相談は2001年以降に5倍に増えており、被害者の75%を女性が占めた。夫による精神的な暴力が認められず、調査官に面会交流を誘導されたケースもあると、「しんぐるまざあず・ふぉーらむ」の赤石千衣子理事長は話す。
目に見えない暴力
赤石氏は「共同親権を導入したら、子どもと女性にすさまじい影響が及ぶ」恐れがあると指摘。「別居から何年たっても妻への執着を消さない夫に襲われている妻は一生危険と隣り合わせ」になると警鐘を鳴らした。
最高裁のデータによると、女性が離婚を申し立てる際に挙げる最も一般的な動機の一つは「生活費を渡さない」など経済的DVとなっている。
元家庭裁判所調査官で、現在は富山大学専任講師の直原康光氏は、家裁では近年、親と子どもの双方から複数回にわたって面接を行うなど、より丁寧なアセスメントを実施するようになったと指摘する。ただ、家裁のリソース不足などを背景に「DVのリスク評価は、それでもなお難しい」という。
親権制度を巡る問題を最も大きく浮き彫りにしているものに、親が外国出身のケースが含まれる。キャサリーン・ヘンダーソンさんはその一人だ。オーストラリア出身の高校教師であるヘンダーソンさんは、1997年にメルボルンで元夫と出会った。結婚後に東京に移動し子ども2人ができた。夫から結婚15周年に離婚を切り出され、ヘンダーソンさんは拒否したという。
ヘンダーソンさん(52)によると、元夫は子どもと共に去り、彼女が子どもに会うことを認めなかった。元夫はコメントを控えている。ヘンダーソンさんは調停を求め、監護の計画や面会スケジュールの案を出したが、そこから一向に前進しなかったと話す。2人の子どもの親権は元夫に与えられ、ヘンダーソンさんの不服申し立ては退けられた。
この3年間、子どもと話す機会がなかったヘンダーソンさんは日本で暮らすのは「非常にストレスがかかる」としながらも、何かが変わることを期待し、できる限り長く住み続けるつもりだと語る。約2年前に電車内で娘を見かけたが、彼女を混乱させることを恐れ、話しかけずに電車を降りたという。
日本は、一方の親による子どもの連れ去りを巡って西側諸国から批判を浴びてきた。長年にわたる外交的圧力を受け、日本はG7メンバーでは最も遅い2014年にハーグ条約締約国となった。発効後の日本による同条約の運用は「他の締約国と比べても遜色ない」と京都大学の西谷祐子教授はみている。同条約は、一方の親に国境を越えて不法に連れ去られて留置された子どもについて、両親の国籍は問わず、原則として元の居住国へ返還すると定めている。
ただ、子どもの親権や面会交流を巡って日本国内で争っている親たちは、異なる扱いをますます不公平と感じている。
特につらいのは調停ペースの遅さだと北條さんは語る。妻と子が過ごしていた家の2階に行くのがつらく、2人がいなくなってからほとんど足を踏み入れていないという。
「父親として子どもの成長を見て感じて共に人生を歩みたい」と北條さんは話す。「会えたら、たわいもない話をしたい。定期的に会えるようになったら、子どもが喜ぶところに連れて行ってあげたい。野球とか釣りとか。息子はウルトラマンが好きだったが、今でも好きなのかなと、思いながら過ごしている」。
原題:Japan Tries to Fix Child Custody System Under Fire on All Sides(抜粋)
アクセス数
総計:367 今日:1 昨日:0