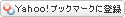令和3年8月27日、月刊Hanadaプラス
実子誘拐を黙殺する日本のメディア|上條まゆみ
「私の子供たちは日本で誘拐されています」。メダルラッシュに沸いた東京オリンピックの陰で、命がけのハンストを行っていたフランス人男性、ヴィンセント・フィショ氏。BBCをはじめ、海外メディアが続々とこの問題を報道するなか、日本のメディアは「報道しない自由」を行使。日本の司法は腐っているが、日本のメディアも腐っている――。
私の子どもたちが日本で誘拐された
日本在住のフランス人男性、ヴィンセント・フィショ氏は、2021年7月10日から30日まで21日間にわたり、オリンピックスタジアム近くのJR千駄ヶ谷の駅前でハンガーストライキを行った。
ヴィンセント氏が命を賭けて訴えたのは、妻に連れ去られた子どもとの再会である。ヴィンセント氏によると、彼の妻は2018年8月、彼に無断で、当時3歳と1歳の子どもを連れて家を出て行った。
ヴィンセント氏が来日したのは15年前、24歳のとき。金融機関の駐在員として東京にやってきて、同い年の日本人女性と知り合った。意気投合して結婚し、2015年には長男が誕生。ヴィンセント氏が公開しているHPによれば、出産後、妻は家事や育児を放棄するようになり、夫婦仲が悪くなった。その後、妻はヴィンセント氏に無断で、不妊治療の際に冷凍保存してあった精子を利用して2人目を出産。ヴィンセント氏は妻に離婚をもちかけたが、妻は拒否した。
そんなある日、ヴィンセント氏が仕事から帰ると、家の中はもぬけのから。家財道具も車も、妻子の姿も消えていた。
「警察に行き、子どもの誘拐を訴えましたが、何の協力も得られませんでした。それどころか、私が子どもを連れ戻そうとすれば、誘拐罪で逮捕するとまで言われてしまいました。弁護士にも相談しましたが、いったん連れ去られてしまえば子どもに会えなくなってしまうのが日本の現実だ、と……」
その後、ヴィンセント氏の弁護士と妻側の弁護士が協議した。「子どもに会わせてほしい」という彼の訴えに、妻側の弁護士は「自身のDVを認めれば会わせるが、認めなければ会わせない」と言ってきた。
ヴィンセント氏は、DVなどしていない。だから、DVを認めなかった。実際、その後の調停でヴィンセント氏のDVはなかったとされ、妻側も主張を撤回している。
調停では、子どもの監護者指定をめぐる話し合いがもたれた。連れ去りによって妻が子どもの監護を行っている現状があることから、「継続性の原則」が適用され、子どもの監護者は妻に指定された。妻はヴィンセント氏に子どもを会わせることを拒否しており、司法もそれを許している。現在は離婚裁判中である。
今日までおよそ3年間、ヴィンセント氏は子どもに会えていない。
実子誘拐を容認する日本の司法
なぜヴィンセント氏は子どもに会えないのか。
家事事件にくわしい栗原務弁護士は、
「その背景には、日本における法制度の不備と裁判所の不適切な運用実務がある」と言う。
日本は、離婚をした際に片方の親だけが親権をもつ単独親権制度を採用している。しかし、離婚後、どちらの親が親権を得るのかについての基準は法制化されていない。また、離婚前に子どもの監護者の指定が問題となる場合も、どちらの親を監護者として指定すべきかについての基準は法制化されていない。
その法の不備を裁判所の裁量的判断が埋めているが、裁判所における親権者または監護者の判定においては「現在、どちらの親が子どもと暮らしているか」という点が重視され、子どもが片親と暮らさなくなった経緯(同意に基づく別居か、連れ去りによる別居か等)の当否や、子どもと暮らしている親の都合により他方の親と子どもの関係が断絶されていることの当否等が軽視されている。
つまり、先に子どもを連れ去り、子どもを引き離した側が有利となる。
そもそも、片方の親の同意なく一方的に子どもを連れ去る行為は未成年者誘拐罪にあたる。しかし、なぜかそれは不問に付され、連れ去られた子どもを連れ戻す行為は未成年者誘拐罪として逮捕されてしまう。
子どもと引き離された親が、子どもと交流し続けることを担保する手続きがないという問題もある。裁判所が面会交流を認めても、強制力がないため、引き離されている親と子どもは子どもと同居している親の都合により簡単に断絶される。
「結婚生活で揉めて、妻が『実家に帰らせていただきます』と子どもを連れて出て行ってしまうのは、日本では昔からよくあることだった。出て行かれる側は相当ひどいことをしたんじゃないの、それならまあ仕方がないよね、といったような偏見が未だ根強い。しかし、一方の親が他方の親の同意なく子どもを連れて家を出ていくことは、未成年者誘拐罪にあたる。それにもかかわらず、警察も弁護士も裁判官も調査官までもが、原則論を無視し、また、例外的に正当化される事由の有無を一切検討することなく、法的な正当化根拠を曖昧にしたまま、連れ去りや親子の引き離しを容認しているんです」(栗原弁護士)
日本は子どもの拉致国家
親子が片方の親によって一方的に引き離されている状態は、子どもの権利を侵害している。1989年に国連総会で採択され、1990年に国際条約として発効した「児童の権利条約(子どもの権利条約)」に、日本は1994年に批准しているが、その9条1項には「児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する」と定められている。
また、9条3項は「児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する」と定めている。子どもの連れ去り、そしてその後の親子の断絶は、明らかに国際条約違反だ。
「子どもの権利を守ってほしい」
これまでヴィンセント氏は、さまざまな法的行為を試してきた。日本の警察や司法には頼れないと知ると、EUや欧州議会に訴えるほか、2019年にはフランスのマクロン大統領にも面会し、支援を求めた。マクロン大統領は、ヴィンセント氏の訴えを受理し、日本に抗議した。しかし、事態はいっこうに改善しない。
その間にも、妻側が提起した離婚裁判は粛々と進み、年内には判決が出る見通しとなった。ヴィンセント氏は、今は子どもの親権者だが、裁判で離婚が成立すると、監護権をもつ妻が子どもの単独親権者となってしまう。
婚姻中で共同親権の状態にある今でさえ夫に子どもを会わせない妻が、単独親権者となってから、子どもを会わせるようになるとは思えない。ヴィンセント氏は危機感を募らせた。
そこで始めたハンガーストライキ。
ヴィンセント氏を支えるハンガーストライキ支援事務局によれば、このプロジェクトの立ち上がりは今年4月。オリンピックのタイミングに合わせてハンガーストライキを行うことで注目を集め、日本における子どもの権利侵害を広く訴えようと考えた。
マクロン大統領にもコンタクトをとっていた
ヴィンセント氏自身は、実際に子どもに会えるまでハンガーストライキを続ける覚悟だった。ふらついて倒れた際にけがをした手の手術を余儀なくされたことで、30日をもってハンガーストライキは中断している。
「子どもに会いたい」というヴィンセント氏の望みはかなわなかったものの、ハンガーストライキは事態の改善に向けて一定の効果があったと支援事務局では見ている。
「ヴィンセント氏の訴えが重大な子どもの人権侵害だということが理解されたのだと思います。初日から海外のメディアの取材が入り、フランスやイタリア、アメリカなど欧米諸国では大きく報道されました。最終的には、BBC(英国公共放送)で放映され、日本でも配信されました。ヴィンセント氏と同じように親子断絶に苦しむ当事者がたくさん現地に訪れ、これが個人の問題ではなく社会の問題であること、男女問わず誰にでも起こりうる問題であることを世間に示してくれました」(支援事務局)
日本のメディアは消極的だったが、これは想定内。日本にはこれまでの経緯から、日本のメディアが子どもの連れ去りや親権がからむ報道に、必要以上に慎重であることはわかっていた。実際、一度、記事になったものの、ヴィンセント氏の主張だけで相手方の主張が併記されていないとの理由で削除されたWeb記事もあった。
ヴィンセント氏は、フランス大使館を通じてマクロン大統領にもコンタクトをとっていた。マクロン大統領が現地を訪問し、直訴の機会が得られるのではないかとも期待された。結論として訪問は実現しなかったが、マクロン大統領は7月24日に行われた菅義偉首相との会談で、ヴィンセント氏が訴える子どもの連れ去り問題に言及。その結果、日仏共同声明のなかに領事協力として「両国は、子の利益を最優先として、対話を強化することをコミットする」との文言が盛り込まれた。
さらに7月30日には、パトリシア・フロアEU駐日大使をはじめフランスやドイツ、イタリア、スペインなど欧州連合(EU)加盟国の駐日大使ら9人がヴィンセント氏を訪問し、連帯の意向を示した。
「これらのことは、ヴィンセント氏にとってはもちろん、日本人当事者、共同親権・共同養育支持者にとって決して小さくない成果だと思っています」(支援事務局)
子どもに会うことはできるのか
さて、今後だが、ヴィンセント氏は子どもに会えるのか。ヴィンセント氏が望んでいるのは、離婚をしても子どもの養育に半分携わる、欧米では当たり前のスタイル。はたして、それは実現するのか。
「正直、見通しは甘くないと思っています」と言うのは、ヴィンセント氏の代理人を務める上野晃弁護士。たしかにハンガーストライキには、一定の効果があった。終盤を迎えていた離婚訴訟に和解のテーブルが設けられる可能性が出てきたのも、ハンガーストライキが与えたインパクトのおかげだ。しかし、形式的に和解協議の機会が与えられただけでは、結局、双方の意見が一致せず、和解は決裂する未来が見えている。
「家事事件にせよその他の訴訟にせよ、裁判官は、当事者が抱く、『自分に不利な判決が出るのではないか』という不安を利用して和解を引き出します。例えば100万円を返してほしいという訴訟の場合、訴えた側が、『判決だと50万円くらいしか返ってこないかもしれない』と不安を抱く一方、訴えられた側が、『判決だと100万円を全額返せという判決が出るかもしれない』と不安を抱く。その両者が抱く不安を利用して『80万円でどうですか』と和解に導くことができるのです。しかしながら、今回の件を含めて日本の家事司法のように、子どもを連れ去った側に、確実に親権が得られる仕組みになっており、さらに連れ去られた親に子どもを会わせるか否かも連れ去った親に多大な決定権が事実上与えられている現状では、子どもと同居する相手側に、たとえば『ヴィンセントさんと子どもたちとの交流を年の半分くらい確保する』といった和解に応じる心理的動機付けが極めて乏しいと言わざるを得ません」
要するに、連れ去り勝ちを容認する法の運用実務がある限り、ヴィンセント氏の現状は好転しない。子どもの権利は守られない。
上野弁護士は、裁判所に法の運用実務を改める努力をしてほしいと言う。
「具体的には、フレンドリーペアレントルールの導入です。フレンドリーペアレントルールとは、子どもの親としての関係で、片方の親と友好的な関係を築くことのできる親のほうが親権者にふさわしいとするもの。このルールの導入によって、子どもの連れ去りや親子の引き離しは減るはずです」
個々の案件の積み重ねによって法の運用実務は変わる。弁護士や裁判官、調査官など家事事件に携わる人たちみんなが子どもの連れ去りや親子の引き離しに厳しい目をもつことで、少しずつ運用実務は変わっていく。
「当事者ではない、まったく利害関係がない人に子どもの連れ去りや親子の引き離しについて話すと、たいていは『それは酷いね』『おかしいね』といった反応です。それがふつうの感覚なんです。この問題を広く世間に知らせ、まわりの声を大きくしていくことが大切なのだと思います」(前出・栗原弁護士)
ヴィンセント氏の起こしたアクションは、その一助となったと思われる。それにしても、日本のメディアがヴィンセント氏のハンガーストライキをほとんど報道しないのはなぜなのだろうか。
アクセス数
総計:1053 今日:1 昨日:0