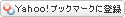令和元年5月30日、HUFFPOST
「友人にも妻にも話したことはない」離婚家庭の息子たちが明かす親子の関係
15万3600件。これは1988年、今から30年前の日本の離婚件数だ。婚姻件数が70万7716件なので、単純計算すると約21.7%の離婚率ということになる。
しかし、「親は二人」がまだまだ一般的な日本では、ひとり親家庭の親子関係はちょっと特殊とされる。もちろん、“親”なる存在がひとりきりだからである。
ひとり親家庭で育った子どもたちは、親とどんな関係を築くのだろうか。その当事者として、これまであまり語られることのなかった「母と子どもの関係」に注目し、女性編に続いて3人の男性に話を聞いた。
「こんなこと、友人にも妻にも話したことありませんよ。話したいことでもないし、話す機会もない」と、ある男性は語った。母との距離に人知れず悩む彼らの本音とはーー?
母との適切な距離は、最後までわからなかった
「結局、最後まで適切な距離感はわからないままでした」
7年前に亡くなった母親について、鈴本真二さん(仮名)はこう回顧する。
鈴本さんは、島根県生まれの41歳だ。両親が離婚したのは、小学校に上がる直前。母は、鈴本さんと3歳年上の姉きょうだいを連れて、実家に身を寄せた。
「よくある貧困母子家庭ですよ。母の帰宅は毎日夜中で、祖父母が親代わりでした」
「姉は中学に入って早々に非行の道へ走り、それを横目に見て育った僕は、小学校高学年からラジオや音楽、映画、雑誌、ゲームなどのカルチャーにどっぷりハマっていきました。放課後や休日は自宅に友だちを呼んで、自分にあてがわれていた家(母屋)の離れでたむろしていました」
中学時代は、街にある5軒のレンタル屋をめぐって映画のビデオをどっさり借り、それらを観て過ごすのが週末の楽しみだった。
「土曜日はもう一つ、大切にしていた時間がありました。深夜の12時半とか1時まで起きていて、仕事から帰宅した母親と、録画した『平成教育委員会』を観るんですよ。それが唯一の母との時間でしたね」
母は深夜まで働き、姉は不良仲間と外で遊び、鈴本さんは友人と濃密な時間を過ごす。それぞれが異なる世界で生きる鈴本さん家族が共有するのは、週に1度、1時間の『平成教育委員会』を一緒に観る時間だけだった。
しかし、そのつながりはあまりに危うく頼りなかった。鈴本さんは、ある些細なきっかけで家族との距離感を見失ってしまったのだ。
「ある夜、離れから母屋に戻ろうとしたときに、カギが締められていたんです。なぜだかすごくショックで、それから家族には心を閉ざすようになりました。誰がどんな意図でそうしたのかはわかりませんが、あの瞬間に家族とのつながりが切れてしまった」
暗闇でひとり立ち尽くした鈴本さんは同時に、「僕たち3人はやっぱりそれぞれが別々の人生を歩むんだな」と悟ったという。
「家族との関係をどうにかしなきゃとは思っていませんでした。当時はもう、血縁関係が嫌になっていて、友だちとの関係のほうがよっぽど濃いと考えてもいました」
高校卒業後は、18歳で上京。母親のことを憎いと思ったことはないが、母親とどう接するのがいいのか、何を話せばいいのかは、ずっとわからなかったと明かす。
「いつも『これをやっとけば喜ぶんだろうな』って他人事みたいな理由しか見つけられないんですよ。30歳で今の勤務先に入社したときも、『母でも知っている大手企業だし、息子が就職したら喜ぶだろうな』と思って報告しましたし」
事実、母は喜んでいた。とはいえ、鈴本さんが直接言葉をかけられたのではない。母の死後に、元同僚からそう聞かされたのだ。
「母にステージ4のすい臓がんが見つかったのは、僕が34歳のとき。当時は2週間に1回、田舎に帰っていました。それでも、僕はゆがんでいるんです。『顔を見せることがいいんじゃないか』と思ってきたくせに、弱った母の姿を見たくないから『行ったって仕方ないし』と地元の友だちと遊んでみたりしましたね」
母の闘病中は、『ワクチン治療に一縷の望みを託すべきだ』と母を説得し、治療費を出したりしたという。当時の彼女を連れて、結婚相手として紹介したりもした。すべては、そうしたいと望んだからだ。
「それでも、どこかで『息子だったらそうすべきなんじゃないか』『結婚という一般的な幸せを見せたらいいんじゃないか』と考える自分がいました」
一つひとつの言動は、彼を孝行息子に見せただろう。しかし内実は、彼は母との距離を最後まではかりかねていたのだ。
現在は、妻と二人で暮らしている鈴本さん。妻との関係は「家族というより個と個のつながり」だと話す。
鈴本さんは故郷を離れた地で、「血縁よりも濃い関係」が結べるかけがえのない相手を見つけた。
思春期、母親を「おばさん」と呼び始めた
田端弘さん(仮名)は、福岡県出身の44歳。両親が小学校低学年で別居し、10歳のときに離婚。思春期、彼は母親を「おばさん」と呼びはじめた。
「母ひとり、子ひとりの母子家庭だったので、精神的な部分での母子密着がすごかったんでしょうね。離婚のドタバタもあって小六まで一緒に寝ていましたし、小学生の頃は母親に強く依存していたと思います。でも思春期になって、そんな自分がすごく嫌になって……」
結果、自分と母親とを引き剥がすかのように使い始めたのが、「おばさん」という呼称だった。一方で、母親を理解したいという気持ちも強かった。
「母は、大手電機メーカーの正社員として勤務しながらも、高卒の一般職ゆえに会社では嫌な思いをすることが多かったのでしょう。会社から帰宅して、『悔しい』と泣くこともありました」
「そんな様子を見ていたからか、中学生ながらに社会学やフェミニズムに目覚め、宮台真司や上野千鶴子を読むように。『なぜ女性は女性だというだけで差別されなければならないのか』と考えたかったんだと思います。母親の苦労を言語化したい気持ちがあったんでしょう」
中学、高校に上がっても、家庭内に二人きりの密接な関係は続く。そのため、十分に心の距離が取れないまま、田端さんは相反するアンビバレントな思いを抱き続けた。
「何かと干渉してくる母親をウザいと感じながらも、“母親は自分だけに奉仕するもの”みたいな感覚は、ずっと持ち続けていたような気がします」
それは、いまだに続いている。
「いまでも、母親に相対すると思春期男子に戻ってしまうんですよね。素直になれなくて、『なんだよウザいな』みたいな接し方しかできない。一方で甘えも断ち切れていなくて、親は自分のことを愛していて当然だというような感覚もあるんです」
田端さんは、大学進学と同時に上京。故郷を離れてから今まで、母親との微妙な距離感は変わらないままだ。
たびたび電話をして『振り込め詐欺に気をつけろ』と忠告する一方で、年に1〜2回、一緒に行くと決めている国内旅行では、旅行代金をかなり多めに出してもらえるようせがんだりもする。
「でも、けんかばっかりしてるんですよ。いまだに、福岡にいたころのお互いの態度の問題で言い合いになって、電話を切ったりして。たまにオレは40にもなって何をやっているのだと思ったりもしますね(苦笑)」
「父親もいる家庭に育っていたら、思春期にもう少し母親と距離が取れて、今の関係も変わっていたのかもしれませんね。妻の方が、ときに受け流して、ときにおだてて、よっぽど僕の母親とうまくやっていますよ」と田端さんは話す。
彼は、いまも母親を「おばさん」と呼ぶ。
「事情を知らない周りの人には引かれるけど、特別な意味はないんですよ。急に『お母さん』とか呼んだら、母親ですら『何ね、あんた気持ち悪い』みたいなことを言うと思う」
母親との距離を取ろうと使い始めた「おばさん」。その呼称は、二人が積み重ねてきた不器用な愛情を示すようにも映った。
言えない本音は、すべて姉に打ち明けていた
東郷大地さんが遅れた反抗期を迎えたのは、大学生のことだ。
「高校時代まで、母は“唯一神”でした。逆らうことはもちろんなかったし、母の考えに違和感を抱いても『母が正しいはずだ』と自分に言い聞かせていた。母との関係が変わったのは、大学時代です。家を出て距離を置いたことで初めて母を相対化でき、母も1人の人間なんだと気がついた」
東郷さんは、山口県出身の25歳。3歳で両親が離婚。10歳年上の姉とともに母親に引き取られ、三人暮らしに。中学進学のタイミングで姉が家を出たため、思春期は母との二人暮らしだったという。父の記憶はほとんどない。
「中学校までは、無理をしてでも“いい息子”であろうと努めていました。母に金銭的、時間的負担をかけないようにと、いつも気を遣っていましたね。『勉強だけはしておきなさい』と言われていたので、真面目に学校に通っていて、成績も上位をキープしていました」
周囲は塾に通ったり、流行りのゲームで遊んだりしていたが、それらを母にねだることはなかった。ときに、さみしい気持ちを抑えることもあった。
そんな東郷さんを支えたのは、姉の存在だ。
「人に言えない本音は、すべて姉に打ち明けていました。さみしい気持ちも全部。姉とは、ずっとお互いに何でも話す関係なんですよ。中学までは週末に勉強を見てもらったりもしましたし、今でも頭が上がりません」
高校に進学してからも、母に報いたい、母を喜ばせたいという思いは途絶えなかった。それゆえ、自己主張はせず周囲と波風立てずに協調することをよしとする母の性格を、東郷さんは知らず知らずのうちに内面化していた。
「きっかけは、大学のゼミやサークル活動のなかで、自分には考えを伝えて人を動かすスキルが欠けているなと感じはじめたことでした」。東郷さんは転機を振り返る。
「例えば、アカペラサークルでライブを仕切る担当になったとき、僕は人の顔色ばかりうかがっていたんです。こうしたいという思いはあったけれど、それをどう伝えて、どうやって人を動かせばいいのかがわからなかったんですよね」
なぜだろう? その理由を考えた結果、はっと思い当たる。
絶対視していた母の考えは、ここでは通用しない。母が間違うこともある一人の人間なのだとわかったとき、東郷さんはあまりのギャップに苦しんだ。
だって、大好きな母が間違っているなんて思いたくない。
「以来、母をロジカルに詰めるようになりました。母に逆らったのは人生で初めてでしたね。単純に母親が間違っていることを指摘したい気持ちもあったけれど、とにかく母親を好きでいたいという気持ちで……」
母親が大好きだから、正しくいてほしい、好きでいられる母親でいてほしい。だからこそ、熱がこもりすぎることもあった。
「顔を合わせたときは、特に熱を帯びて。母も頑固なので、二人で何時間も議論することになるんですよ。帰省の際に夜中の3時ぐらいまで延々と話して、結局、あんまり理解してもらえずに『もういい!』って二階に上がる、みたいなことがあったり……」
母と本音でぶつかり合うようになった東郷さんは、今度は正論で母を言い負かした罪悪感に陥ったり、母親をストレスのはけ口にしているのではと悩んだりするようになった。
そんなときの相談相手は、やはり姉だった。
東郷さんは、「悩みを打ち明け合える姉という存在がなく、母親とずっと一対一だったら、どこかのタイミングで”モヤつき”をため込んでいたと思います」と回想する。
「過去を振り返ると、自分でもこじれそうな生育環境だよなと思うんです。でも、僕自身はいい育ち方をしたなと感じている。それは、僕たちが三人だったからかもしれませんよね。僕も姉も、互いを巻き込むことで、うまくガス抜きができていたのかもしれません」
東郷さんは、家族三人で暮らしていた時代、姉と母が言い合いをしている場面をよく覚えている。
「二人が口論になると、よく『大地はどう思う?』って話を振られたんですよ。その繰り返しで、僕たちは関係を良好に保ってきたのかもしれない」
東郷さんは、姉という相談相手がいたからこそ、真正面から母親と向き合うことができた。
昨年、姉の結婚式では、パートナーとの幸せそうな姿を見て、誰より号泣したそうだ。また一方で、「父に会ってみたい」という長年思い描いていた希望も実現させている。もちろん、母を大切に思う気持ちは変わりない。
同じひとり親家庭の親子関係でも、親と子の関わり合いの深さ、きょうだいやコミットする親戚の有無などによって、その家族のかたちはさまざまだ。
ただし、緩衝材になりうる人物がいるかいないかで、一対一の親子関係の風通しはかなり変わってくるのかもしれない。
一般的に、男性は家族のことをあまり語りたがらない。今回、インタビューに答えてくれる離婚家庭育ちの男性にめぐりあうまでは、長い道のりだった。
「人と深い関係を築くのが苦手なんでしょうね。普通はそういうのを家庭の中で学ぶんでしょうけど……」
取材中、鈴本さんが何気なく漏らしたこの言葉を、たびたび思い出す。
事実、家庭とは人間関係のトライアルアンドエラーの場なのだろう。しかし、男性からこんな言葉を聞いたのは初めてのことだった。
どこか心が満たされない“欠け”のようなものは、どんな人にもある。ただ、寡黙に強くたくましくあることを強いられがちな男性にとって、自らの“欠け”を抱いたまま生きる痛みは、女性のそれとは少し違うのかもしれない。
取材に応じてくれた3人の話を聞き、彼らが人知れず抱えてきた過去に、もう少し耳を傾けてみたいと感じた。
(取材・文:有馬ゆえ、編集:笹川かおり)
アクセス数
総計:999 今日:1 昨日:0